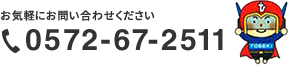No.285
こんにちは♡
5月になり、新しい生活にもなじんできた頃です。
5月病になってはいませんか?
新1年生も緊張から解放され、学校が楽しくなる頃ではではないでしょうか。
義務教育の小学校入学は、住民基本台帳に基づき、満6歳の誕生日以後の最初の
4月1日に、半ば自動的に入学することになります。
近代小学校が出来、約150年経っています。
『小学校』という名称は、貞享(ていきょう)2年(1685年) 今の長崎県・対馬藩で家臣の子弟を教育するために設置された学校が、『小学校』と名づけられたのが始まり。
明治2年(1869年)5月21日、京都で日本最初の『小学校』の開校記念式が行われたそうです。
京都府は道路を挟んで形成された町が集まって、地域的に連合した『町組』という自治組織があり、この『町組』に1校ごと『小学校』を設立する計画をしていたそうです。
明治7年の学校に通っていた比率は、男児46% 女児17% 総計平均32%。
3人に1人の割合しか通っていなかったようです。
ほぼ全員が就学しているといえるようになったのは、明治45年(1912年)の頃。40年以上の月日がかかっています。
それでは『小学校』を作った人は誰でしょう?
調べたてみました。熊谷直孝(くまがいなおたか)さん。
家具屋久右衛門(かぐやきゅうえもん)とも称していたそうです。
幕末の商人で鳩居堂七代目当主。私財と土地を提供し、上京第二十七番組小を、明治2年に開校。
若いころから「頼山陽(らいさんよう)」(大阪生まれの歴史家)らと親交があって、勤皇派(きんのうは)(天皇に忠義を尽くす人たち)町人として有名な方のです。
尊王攘夷派(そんのうじょうい)や勤皇派の公家(くげ)と関わり、倒幕運動(とうばくうんどう)に資金援助をしていたとか…。
明治政府の資金調達に1500両も出していたとか…。
何故、京都が3年早く『小学校』を開校したのでしょうか?
(日本の近代学校制度は、1872年明治5年から)
明治政府の東京遷都で、京都府が衰退するのを危惧(きぐ)し、『教育によって近代都市へ』という意図があったようです。
驚くべきは『小学校』を建設するための費用を、商人や住人の寄付で賄ったこと。
近年も毎年のように、教育を変えようという声を聞きます。
自腹を切ってまで将来の子どもを育てようという、明治の商人の心意気を改めてすごいですね。