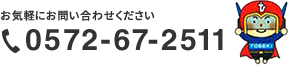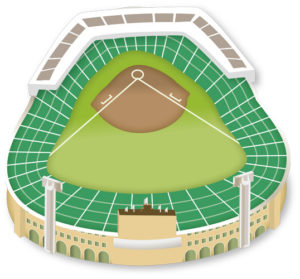№287
こんにちは♡
毎年、夏になると暑さの象徴のような、甲子園の話題が出てきます。
兵庫県西宮市にある阪神甲子園を主会場とし、朝日新聞社と日本高等学校野球連盟が、毎年8月に開催をしています。
前身は全国中学校優勝野球大会。1915年(大正4年)に、大阪府の豊中球場で開催され、1948年(昭和23年)に学校改革に伴って、今の名称になったそうです。
大会旗及び、優勝旗は深紅(しんく)で「深紅の大優勝旗」と呼ばれています。
6月中旬~7月下旬にかけて、地方大会が行われ、すべてノックアウトトーナメント。
全地方大会の出場校は3500校前後(1990年~2011年までは4000校を超えていました)
第二次世界大戦に伴い、1942年~1945年の中断をはさみ、第26回大会(1946年)は敗戦により放棄した、朝鮮・満州・台湾の枠を無くし、19枠で大会を再開しました。
以降は地方の分割が進み、北海道は第41回大会(1959年)から北と南で各1校。東京は第56回大会(1974年)から東と西で各1校。
第60回大会(1978年)以降は、すべての年で1府県1校。北海道と東京は2校の、49代表となりました。(その後、記念大会では1枠増やしたりしています)
第1回全国中等学校優勝野球大会行われた豊中球場は、阪急電鉄の前身、箕面有馬電気鉄道が1,913年(大正2年)に建設・設置された球場ですが、規模が小さく問題となっていたようです。
当時の遠征費はすべて出場校が負担。会期を短縮し、出場校の費用を軽減するために考慮された方法が、複数の球場を設置することを求められました。
そこで、鳴尾運動場を所有していた阪神電気鉄道が応えて、場内に野球用の球場を2面設置し、第3回大会(1923年)から会場が移されました。
学生野球が人気となり、観客が増加。
それに伴い、第9回大会(1923年)。溢れた観客が、球場になだれ込む事件が発生。さらに、球場の水はけの悪さもあり、主催者の大阪朝日新聞は、本格的な球場の建設を提案。
阪神電鉄は、鳴尾村に流れていた申川と枝川(武庫川の支流)を廃川としたあとにできた埋め立て地の大規模な開発を行っており、野球場を建てることになりました。
ニューヨーク・ジャイアンツのホームグラウンド ポロ・グラウンズを参考にし、大会に間に合わせるために突貫工事で球場を建設。
1924年8月1日に球場が完成。この年が十千十二支の最初の年である「甲子年(きのえのとし)」という60年に1度の縁起の良い年であることから「甲子園大運動場」と命名されました。
同年の第10回大会から使用し、戦後初の復活開催となった1946年の第28回大会はGHQに甲子園を摂取されていたため、阪急西宮球場で行われました。この大会は立教大学の教授を務め、戦後GHQの将校として再来日したポール・ラッシュ博士が「若い人に夢や希望を与えるスポーツを復活させることが、戦後の日本にとって必要だ」として、大会の復活に大変尽力をされたそうです。
第40回大会と第45回大会は、大会日数を減らすために、甲子園球場と西宮球場を併用。
でも、不公平だと評判が悪く(甲子園で試合できず敗退した学校から苦情があったそうです)その後は、一貫して甲子園で行っています。
高校野球を主目的に建設された甲子園球場は半世紀あまり過ぎました。
「甲子園」という言葉そのものが、高校野球全国大会の代名詞となりました。
高校野球=甲子園=夏 のイメージですが、歴史を知っている人はどれくらいいるのでしょう?
「甲子園」と一括りには出来ない時間を経てきたのですね。