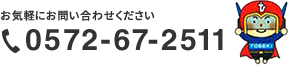№291
こんにちは♡
11月(霜月)15日は、子どもの成長を祝う節目です。七五三です。
七五三とは、言葉として知っているものの、その意味をちゃんと理解しているのは、お子様のいる親御さんや、おじいちゃんやおばあちゃんでしょうか。
三歳になった子どもが、髪を伸ばし始めるお祝い。「髪置(かみおき)」
五歳になった男の子が初めて袴(はかま)をはくお祝い。「袴着(はかまぎ)」
そして、七歳になった女の子が子ども用の付紐(つけひも)の付いた着物から、大人用の女性と同じ幅(はは)の帯を結ぶようになるお祝い。「帯解(おびとき)」または、「紐解(ひもとき)」
3つのお祝いを合わせて「七五三」と言います。
親が子どもの健やかな成長と幸せを願うのは、子どもが大きくなっても変わりません。
昔は多くの家族が揃って着飾り、氏神様詣で(うじがみさまもうで)をしていました。
江戸時代、「髪置」の子に被せる(かぶせる)綿帽子(わたぼうし)に、家紋の屋号を入れる事もあったようです。(商人は宣伝にもなります)
【綿帽子⇒真綿の入った丸みのあるもの。防寒・防塵用に作られました。婚礼の新婦の被り物】
「袴着」の子どもは、家族で記念に揃いの襟や帯飾りを身につけたりもしたようです。
「帯解」の子どもは、氏神様にもう出るとき頭に白い錘頭巾(おもりずきん)を被せることもあったとか。
【錘頭巾⇒額を覆った布の両端に鉛を入れて、風でひらひらとしないように作られた頭巾】
無事に大人になれる子どもが少ない時代です。大人が長生きをするのが難しい時代です。
両親や親族の七五三へも思い入れは、今より大きかったのかも知れませんね。